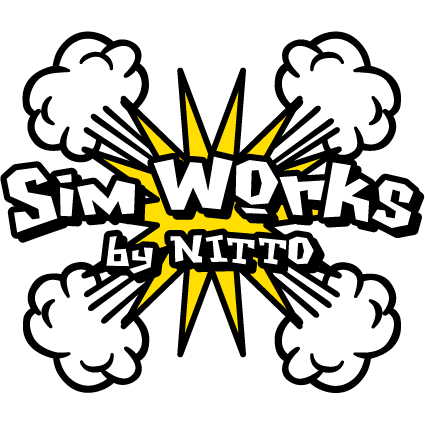[Bike 伊豆 between you and me] サンセットクリーク

夏前に随分と外で遊び、腕も脚も2トーンにくっきりと色が分かれていたのだけど、8月は雨が続き思うように外に出られなかったおかげで焦げた肌もすっかり色褪せてしまった。
消えつつある大腿部の日焼けの境界線にビブショーツの裾をきっちり合わせ、再びの日焼けに備える。
突然舞い戻った炎天の下を往く8月26日。
海岸線を北上し、反対車線の崖を見下ろす先の海。
エメラルドとターコイズを砕いて溶かしたような色彩に伊豆愛は膨れ上がるのだ。
ぼくらの海はこんなにも美しい。
しかしこの日ぼくが向かったのは海ではなく山。
更に言うなら伊豆ではなく、神奈川県南足柄市の山。
Sunset Creek Bluegrass Festivalを目指す。
ブルーグラスというジャンルの音楽の祭典だ。
ブルーグラスという音楽について、どういうものかを説明しよう。
雑に言い放ってしまうと、カントリーミュージックの一種である。
17世紀~18世紀、スコットランドやアイルランドからアメリカに移り住んだ開拓者達が労働の合間にかき鳴らした音楽が原点であり、1940年代に”ブルーグラス・ボーイズ”というバンドが確立した音楽であるため、ブルーグラスと呼ばれることとなった。
動画のように、ギター、ベース、フラットマンドリン、バンジョー、フィドル(バイオリン)という5種類のストリングスで構成されるのが基本となる。
そして、ぼくがどういう経緯の果てにブルーグラスを聞くようになったのか。
そもそもの始まりはニルヴァーナである。
ぼくは青春時代の多くをニルヴァーナに捧げた。(青春時代とは貴重な時間を何かに捧げるためにあるのかもしれない。)
オルタナティブ・ロック、グランジと括られたロックバンドであるニルヴァーナは、ミート・パペッツというカントリー調パンクバンドのカバーをしたことがあり、ぼくがミート・パペッツの音楽に興味を抱くのは自然の摂理だった。
カントリー調のパンクからの移ろいでカントリーに惹かれることになったのも自然な流れだった。
カントリーという大きな音楽ジャンルの中でぼくがとりわけ好んで聞くようになったのがブルーグラスである。

自宅から70km。
神奈川県南足柄市、夕日の滝キャンプ場。
距離も獲得標高も大したことないはずだったのだけど、無慈悲な太陽光線に随分と手を焼いてしまった。
いや、焼いたのは露出した肌全てか。
会場に到着し、受付で3500円を支払う。
このフェスでは観覧客も出演者(プロ、アマ問わず)も皆一律に3500円を支払う。
ブルーグラスという音楽に対して、産み出す側も受け取る側も皆同じ立ち位置で対等なのだ。
今回ぼくの誘いに応えてくれたのはシムワークス総大将田中氏、毎度おなじみYAMABUSHI TRAIL TOUR松本氏、そして我が家の近所に住むプロのトレイルビルダー浦島氏だ。
ぼくらは土曜日から日曜日に掛けて参加した。
ぼくは自転車で参じたが浦島氏は車で向かうということで、荷物を全て預け運んでもらった。
Ridin’ Birdsのスタイルである。
自転車に乗り始めるまではブルーグラスを好む仲間など一人もいなかったのだけど、今では一緒にフェスに行く仲間が出来た。
自転車がもたらしてくれた縁に感謝するのは何度目のことだろうか。
色々な所へぼくを連れて行ってくれる自転車が本当に愛おしい。
主催者の方に少し話を聞くことが出来た。
驚いたことに、もう40年もこのフェスを続けてきたそうだ。
ずっと夕日の滝キャンプ場で開催してきたらしい。
夏フェスの先駆けとも言えるこのイベントの何たるかを少しでも理解していかなくてはならない。


キャンプ場の最奥。
ステージは一つだけ。
森の中だ。
音楽と人が大地と調和できるロケーションが整っている。
200組近いバンドが出演し、各バンドの持ち時間は10分。
朝から真夜中まで絶えずステージは動き続ける。
ブルーグラスワンダーランドだ。



ステージはひと時も休むことなく常に稼働しているのだけど、ステージ以外の所でも絶えずジャムセッションが泉のように湧き上がっていた。
誰かに聞かせる為ではなく、自らの奏でた”音”を”楽”しんでいる。
音楽だ。
想像はしたことがある。
アメリカの古い音楽の祭典を想像はしたことがあるのだけど、それはやはりただのイメージに過ぎなかった。
実際に目と耳と肌で体感してみると、音楽と人と川と森とバーボンは境界線を無くし自由に溶け合っているようだった。
日常を綺麗さっぱり忘れることが出来ていたと思う。
つまらない形容になるが、最高だった。


夏と秋の境を飛ぶ虫達は灯りに集まり、人々は音楽の鳴り響く所へと集まる夜。
ステージの上ではブルーグラッサー達が自由に丁寧に時に激しくアメリカの伝統の世界をかき鳴らしている。
本国アメリカにおいてもブルーグラスはルーツやトラッドに重きを置き、解釈こそ現代的であっても、技法については極端に前衛的なものはあまり存在しないように感じる。
そういうジャンルなのだ。
そして日本ではルーツとトラッドを更に崇める傾向にあるのだなと感じた。
どのバンドがプロなのか、はたまたアマなのか、聞き分けられないほど皆卓越したスキルでぼくらの心を奪うのだけど、起源にあまりに忠実に演奏し歌うのだなと思ったのは正直な感想である。
日本では少なくとも40年間はこの夕日の滝で伝承が繰り返されてきた。
その中で日本的解釈と発展があっても良かったのでは?などと素人が言うのは十分に炎上案件となり得るのだけど、この音楽の分野だけでなく自転車を含めた他のあらゆる舶来の文化にも言えるはずなのだから、恐れずにこのまま記しておこうと思う。

色々と思いを巡らせながらも、基本的にはこのフェスに心を奪われている。
ベースが地面に放置されている風景はとても美しい。

キャンプ場故にテント泊。
野営は殆ど寝付けなくなるのであまり得意な分野ではないのだけど、そうであったとしても夜通し続くジャムセッションを聞いていれば良い。
そして実際にそうなった。

夜の明けない内も絶えずどこかでジャムセッションが繰り広げられていた。
灯された小さな火を交代で見守るリレーのように、音を絶やしてはいけないという責務があるかのように。
ステージでの演奏は終了し、多くの人はランタンの火を消しテントに潜り込んで寝息を立てているのだけど、寝ている人が多いのだから気を遣って楽器を鳴らさない、ということは一切ない。
ここでは誰かが音楽を続けなくてはならないし、そして誰も「うるさくて眠れない」とは言わない。
涼しく、湿度の低い夜明け前だった。

ぼくら4人は一様に来年も参加したいと考えている。
どこまでも自由で、それでいて健全で、美しいイベントだった。
険しい峠道を登って辿り着くというロケーションも自転車で訪れるにはドラマティックである。
このイベントの後、気候は急速に秋へと走り出した。
思い出せる中では一番の夏の終わりの思い出である。
text : Hiroki Ebiko / SimWorks XC Racing [Blog] [Instagram]