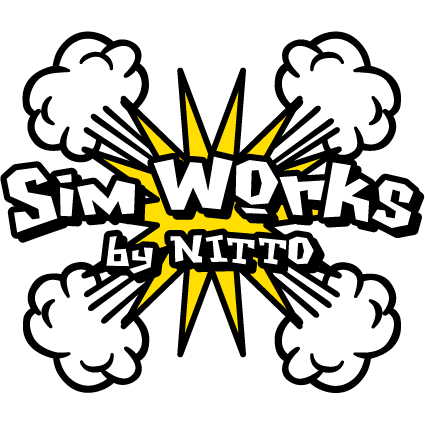ルがつくパーツの重要性(注意勧告)
経験に基づいた実践を行う賢者は、時に不勉強なわたしたちへ含みのある理(ことわり)を示してくれます。それは哲学であり、道徳であり、真理であり、注意勧告でもあったりもするのでしょう。
多くの日本国内で製造するメーカーと共闘をしてものづくりをするSimWorksは、その立ち上がりから15年が経とうとする中で、その理を色々と諭されてきたのも事実です。

自転車という乗り物の大半は人力駆動ということもあり、土台であるシャーシ/フレームに自分というエンジンを乗っけて推進力を自ら生み出す乗り物でありますから、その分離される土台と動力をいかに保持をしていくかが推進力を伝える肝にもなります。
面白いことに、その土台と乗り手が接するパーツのネーミング全てに「ル」がつくことは何かの偶然なのでしょうか。サドル、ペダル、そしてハンドル、この三点のシンプルなパーツたちこそがわたしたちの体を支え、ライディング時においてその体勢を整えてくれる重要なパーツとも言えます。
加えて、それらは優秀なメカニックでなくとも容易に交換が可能であり、そしてその製造工程ですら駆動システムに比べると格段にシンプルであったりもします。(シンプルであるが故に奥が深いのですが)そんな事実を元に今回は「ル」がつくパーツの一つであるハンドルに着目をして話を進めたいと思います。

ルの多様性
近年ではルールに則った多くの競技スポーツの衰退を感じる代わりに、それぞれのプレイヤーの人生観に沿った遊び方が一般的には広がってきていると思っています。それは私たちが人生の中心軸に置くサイクルスポーツだけではなく、さまざまなアクティビティでも進んできているのではないでしょうか。

その流れの中において、使用されるギアの選択方法にも変化が現れてきていると感じるのですが、特に先ほど挙げた3つのルがつくパーツにおいてはそれがさらに明白になってきています。サドルではレザーが復権をしたり、ペダルでもビンディング一辺倒からフラットペダルの移行も始まっています。(これはE-バイクの台頭もかなりの理由になると思いますが。)
25年くらい前のスポーツバイクの世界においては競技から落とし込まれるスタンダードな形状のハンドルバーから、どこぞの勝利者が使用したから選択してもらうという、とても前時代的なPR活動が主軸でしたので、そのあまり違いのない(メーカー名、ロゴ)選択肢の中からどうしても選ばざるを得なかった記憶があります。
しかしながら時が経ち、2000年代のピストムーブメント以降に世界中に広がった、日常的な自転車活用においてのハンドルの性能とは、勝利ではなく自分に対する執着、すなわち心地よさ(それは単に身体的な物事のみではなく)、その見た目、色、そして何よりもユーザーの想像力をもとにした表現方法としても発揮され、とても多様的なものになって来ていると感じています。

実際にそれをデザインする側の人間として、どのような提案をすると、豊かな想像力を持った遊び人たちに支持されるのだろうかと頭は悩まされるのですが、それが一旦支持されたときの高揚感というと、やはりいっぱしに上がるわけなのです。
しかしながら、最初に述べたように物事には理があり、やるべきことと、やるべきではないことはやはり存在するわけで、今まで実際に日東に製造をお願いをしたハンドルバーの約60%くらいは提案の段階、試作の段階、そして強度とスリップ試験の段階で製品として実現しなかったことも事実なのです。

安全と自由の相反性
自由というのは本当に素晴らしいもので、私たちもこの自由主義の中で自由な発想を持って日々、企画生産活動を行っているわけですが、時にその自由にとんでもない落とし穴が隠れている事も経験上感じています。
特にハンドルにおいては、1本のチュービング材をいかに曲げるのか、それは本当に自由なのですが、その素材選び、形状、長さ、加えては仕上げの処理の方法において亀裂、破断、(そしてあまり多くの人が気にしていないけれども)最も恐ろしいハンドルスリップへとつながってしまいます。
SimWorksは以前よりクロモリでのハンドル製造を長年行って来たのですが、疫病の流行と共に突如やって来たアウトドアブーム時代において、クロモリ材を使用した黒仕上げのハンドルの生産をストップしました。

クロモリの黒色ハンドルは黒電着という技法を用いて製造するのですが、それまで通りのローレット(センター部の滑り止め)仕上げでは、幅が広くなっていくハンドルに対しての固定力が足りなくなってしまい、安全を考えて、止むを得ず生産停止としたのでした。(しかしながら追記しますが、そのセンターローレット固定力問題も日東の日々の努力によって、無事に解決がされましたので、黒色のクロモリハンドルが再登場する日も近いということをここにお伝えしておきます。)
また古くからのSimWorksファンの方はご存知と思うのですが、初期のクロモリステムは現在私たちが使用するオリジナルの4本ボルトのフェイスプレートではなく、2本止めのスチール製だったのです。

少なからずすっきりとした見た目の2本止めのクラシックスタイルが好ましいという声もあったのですが、わたしたちの製造するハンドルの幅や形状がどんどん変化をする中で、より固定力の高い方法を取っていくことが、わたしたちの想像力をとめない唯一の方法であったために4本止めに切り替えました。(Gettin’ Hungry Stemは、クラシックスタイルという特徴で、クローズド1本止めを継続して来ましたが、今の在庫限りを持って終了、今後は4本止めのオープンスタイルへの変更を予定しています)
自転車のパーツというものはとても面白いもので、ユーザーの自由な考えを元に、さまざまな異なったメーカーのパーツを組み合わせて1台の自転車にすることが可能です。しかしながらそのパーツごとにも相性があり、現在のトレンドにもなっている過度なバックスイープを持ち、かつ幅広のハンドル幅に対して、先に挙げたような1、2本止めのステムを使用した時の相性は、どんなテスト機関を利用してもスリップテストには通らないことは事実です。

実際に他社の幅広、バックスイープハンドルをGettin’ Hungry Stemに装着をして走行中にハンドルがスリップして回ってしまい転倒(幸運にも怪我をすることはありませんでした。)という事例も出て来ています。
また過去に倒産や売却をやむなくしてしまった完成車メーカーやパーツメーカーのほとんどが、このコクピット問題に起因する問題がほとんであるという事も覚えておくと良いかもしれません。
正しい製品開発を
今一度基本的なお話をします。なぜわたしたちは国内の経験豊かな自転車メーカーと仕事をするのか、それはやはり彼らと同じ考えを信じて共有しているからということに尽きるわけです。
100年以上の歴史を持つ日東や三ヶ島製作所の関係者様が時々話をしてくれる過去の出来事、楽しい話、美しい話、そしてモノづくりにおいて一番大切な事、すなわち安全第一の話。

事故は起こってしまうと誰も幸せになりません。自分が使用する自転車が正しく安全に考えられて組み立てられているのかどうか、今一度立ち止まり考えてみるのもとても大切だと思います。
あまり過度な注意勧告は文化縮小につながるのでわたしたちも好むところではないのですが、正しい情報共有が、この芳醇な自転車文化発展のためには必要であると思っています。私たちはSimWorksが信じている自転車という世の中で一番豊かな道具を、世界中のすべての人たちに正しく利用してもらい、その人生をさらに豊かなものにしてもらいたいと心より願い、生産活動を行っています。

これから実際に多くの新製品をご紹介することができると思いますが、それらすべての製品において、わたしたちが想像できる最大限の利用場面を踏まえた上で、安全第一での設計、生産していますので、なかなかスローペースになりがちなのですが、その正しさだけは決して忘れることなく活動に努めていきたいとこの場を借りて誓いますので、引き続きみなさまのSimWorksへのご愛顧とともにサポートを何卒よろしくお願いいたします。